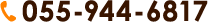『リノベーション』カテゴリーの投稿一覧
- 節水タイプのトイレに交換するときの注意点
- 2016.09.26 トイレ, リノベーション
-
お客様から、節水型の洋式トイレに変更したいと要望が多くあります。
おおよそですが、
1990年代の洋式トイレですと、1回の流量が、大で15L前後の水が使われます。
それ以前の、水を流すレバーに大小の区分けのない洋式トイレですと、20L前後の水が使われていました。
最近では1回に流す水の量が、6Lとか5L未満のトイレもあります。
この時、節水型のトイレに交換したいとの要望を沢山伺いますが、ここが単純にはいかないのでご注意を。
そもそも、排泄物を流すために必要な水をです。
この水を少なくするとはどういうことか???
流す水を少なくすることですから、流す力は弱くなります。
この力が弱くなっても流れるかどうかを、きちんと検討してください。
特に、戸建て住宅の場合、
- トイレの設置位置が、浄化槽や公共下水までの距離がある。
- 汚水配管が床下をとおっている。
- 過去にトイレがつまってしまったことがある。
上記のひとつでも当てはまる場合、ほどほどの節水機能にしておくほうが良いです。
配管が詰まってしまった場合、最悪のパターンでは
2階のトイレが便器から水漏れして
1階まで水浸しになってしまうことも。。。
なにも考えず、「節水トイレは流す水の量が少ないからお得ですよ。」という営業には
「途中で配管がつまったりしない?」と聞いてみてください。
「問題ないですよ。大丈夫ですよ。」と即答する人は事実を知らない可能性が非常に高いので
避けたほうが無難です。
検討します。といって帰ってもらいましょう。
プロなら、配管経路と勾配が、
気にならないはずがありません。
必ず調べることです。。
節水型トイレは、省エネの一環として普及してきました。
しかし省エネのためにトイレが詰まってしまっては元も子もありません。
つまりを直してもらうのにお金がかかっては、
家計にやさしくない省エネになってしまいます。
わからないことがあったら、どんな小さなことでも聞いてください。
水回りのプロから勧められるトイレの秘密をお伝えできます。
- 浴槽やユニットバスの防水は大丈夫ですか?
- 2016.09.16 バスルーム
-
浴槽やユニットバスの防水について、ハウスメーカーは
本当のことを教えてくれません。
浴槽やユニットバス接合部にはコーキングが施されています。
このコーキングは経年劣化で欠けやひびがでてきたり、剥がれてきます。
施工後の保証期間は、メーカーで5年程度のものがほとんどです。
問題なのが、その後についてですが、メーカー保証外なので
万が一水漏れを起こしていたら。。。。
この水漏れというのは厄介で、漏れていても
被害が出るまで気が付かないのです。
そして水漏れの被害というのは、大きな被害になります。
下地が腐ってしまい、建物の浸食・劣化に直結します。
恐ろしいシロアリ被害や家の腐食など、せっかくの住まいが
数年で傷んでしまう可能性があるのです。

またコーキングの劣化による水漏れが原因で
バスタブにヒビなどの損傷がなくても
バスタブごと交換しなくてはいけない状態に
なることもあります。
業者に防水工事をお願いするときの注意点もあります。
業者によっては、使用年数で「お風呂を新しく交換しましょう」
としきりにお風呂の交換工事を勧めてくる業者もあります。
その場合は、なぜ交換したほうが良いと判断したのか
その判断理由を尋ねてください。
うまく説明できずに、「○年ぐらい経過しているから」と
年数だけを理由に交換を進めてくるケースが多々あります。
さらに、「いまなら特別価格で」といった費用を安くする営業
をしてくるかもしれませんのでご注意。。
- トイレの水がでない!!そんな時の原因に多いのが...
- 2016.09.01 トイレ, リノベーション
-
トイレの水が出ない!意外な原因とかしこい対処法って?
「トイレの水が出ない」というトラブルも水が止まらないケースと並んで多いもの。便器に水が出ないとなれば汚物を流すこともできず、これも一大事です。水が出なくなったらすぐにすべき応急処置の手順から根本的な原因を突き止める方法までをご紹介します。
トイレの水が出ない原因って?
トイレを流そうとハンドルを回したものの、何度試しても水が流れてこない…。考えただけでもひやひやしてしまいますよね。しかしこういったトラブルは、水が止まらないというトラブルと並んでよく起こりがちなもの。
便器内の汚物は、バケツで水を汲んできて注ぎ込むと簡単に流れます。まずはこちらで応急処置を行い、その後落ち着いて原因を突き止めましょう。
まずはタンクのフタを外し、中に水があるかどうか確認します。水がある場合は、給水管からタンクへの水の供給は問題なく行われているが、タンクから便器への排水に問題があるということになります。
よくあるのが、タンク下部にある「フロートバルブ」という部品とハンドルアームをつないでいるクサリがはずれたり切れたりしているケース。
こうなるとハンドルを回してもフロートバルブが動いてくれないので、排水口はふさがったままに。当然タンク内の水は便器に流れることができません。レバーのフックにクサリをかけなおしたり、新しいクサリと交換しましょう。
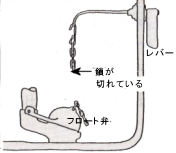
画像元:住まいの宝箱
応急処置として、クサリを購入するまでの間ビニールひもなどで代用することも可能です。ひもは少したるませて結びつけなければなりません。古いクサリを外して同じ長さに切り、調整するとうまくいきます。
タンクに水がないときは、浮玉を下げてみる
反対にタンクに水がない場合は、そもそも給水管から水をうまく取り入れられていないということです。まずは止水管が閉まりすぎていないかチェックしましょう。
止水管に問題がなければ、「浮玉」という部品に原因があるのかもしれません。タンクへの給水をつかさどる「ボールタップ」という部品は、この浮玉の位置によってその必要性を判断します。浮玉が下がっていれば水位が下がっていると判断し、給水を行うのです。
実際には水位が下がっているのに、何らかのトラブルで浮玉が下がらなければ、ボールタップは水量が減っているのに気づくことができません。その結果タンク内の水がなくなり、便器からも水が出なくなるというわけです。
タンクのフタを外して、浮玉の状態をチェックしてみましょう。タンクの内側の壁に引っかかっているのを正したり、手で下に押すだけでなおる場合もあります。
それでも解決しない場合は、浮玉とボールタップの接続がゆるんでいるのかもしれませんので、しっかり閉めなおしましょう。浮玉の支持棒をペンチなどで横から見て少しへの字になるように曲げるのも、ひとつの方法です。
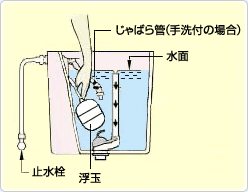
画像元:TOTO
これらの方法により浮玉を適切な位置まで下げることができれば、タンクへの給水がはじまるはずです。順序を踏んで確認と対処を進めていくことが、トラブル解決の鍵となります。
タンクにペットボトルをいれてませんか?
以前からの知恵で、タンクの中にペットボトルを沈めて、流れる水を調節して水道代(下水道利用料金)を節約する技が流行しました。
実際のところ、我が家でもやっていました。。。やっていましたというのは、このペットボトルがよく詰まるのです。
タンクの中で動かないように固定していた紐がなぜか緩んでしまいタンクが当初固定していた位置から浮玉やフロート弁と干渉してしまうのです。干渉していると、水が出なかったり、流れたまま止まらなくなります。でないのはまだしも、節約するはずが流れっぱなしってね。。。
時には一晩中流れっぱなしのこともありました。なので今はペットボトル節水案は破棄しました。
もっとも、いまではタンクも進化して、節水型になってきているのでこのような策は不要です。
逆にこれ以上節水しようとしても流れるものが流れなくなることもありますので、やらないでくださいね。
配管を詰まらせたら、簡単には治らなくなりますので。

画像元:NAVERまとめ
従来のタンクは一回の水量が13L、30年以上前だと20Lの水を流します。
最新の節水型トイレは、一回で6L以下ですから、これだけで節水効果は高いです。
- ビルトイン浄水器が持つ多様な機能に注目
- 2015.12.26 バリアフリー, リノベーション
-
ミネラルウォーターに対する関心は引き続き高く、飲料としてだけでなく料理や洗顔に利用する人も増えてきています。こうした要望に応え、最近では浄水器が標準として取り付けられる新築の家もあります。その際に選ばれているのがキッチンやシンクの下に設置するビルトイン型浄水器です。アンダーシンク型とも呼ばれるこのタイプの浄水器はいくつもの利点があるため人気が高いものの、この取り付けには専門業者による工事が必要になるため、リフォームするタイミングを活用して設置をするケースが多く見られます。
ビルトイン型はシンク周りがすっきり見えるため、景観を損なわないタイプとしても注目されています。最も簡易的な蛇口直結タイプの浄水器はほぼ毎月カートリッジの交換を必要とする一方、ビルトインタイプは一年に一度交換すれば良く、カートリッジの入手を十分前もって行っていれば、その他の手入れはそれほど必要としません。また最近では交換時期を忘れないためにデジタル表示されているタイプもあります。
カートリッジ内の構造はシンクに据え置くタイプとほぼ同様であるものの、カートリッジそのもののサイズがかなり大きいことからフィルター層の数が多く、塩素や有害物質を取り除く浄水能力は非常に高いと言えます。またろ過できる水量が豊富なことに加えて、最近のモデルでは酸性とアルカリ性のイオン水に調整する機能も搭載されています。こうした多様な機能とコストパフォーマンスの良さがビルトイン浄水器の強みと言えるでしょう。
- ウォーターサーバの利用者が増えているのはなぜ?
- 2015.12.26 リノベーション
-
かつては会社やオフィスのみを顧客としていたウォーターサーバー市場は、一般家庭を顧客として取り入れ始めて以来拡大を続け、現在では1千億円を超える規模の業界に成長したと言われています。いつでも必要な時に冷水と温水が飲めるという手軽さが受けて家庭内での用途が広がり、その結果多くの業者が参入するという結果につながっています。では新たにウォーターサーバを利用しようとする場合、どんな点を念頭に置いて決定をしたら良いのでしょうか。
まずはどのタイプの水を飲みたいかを決める必要があります。不純物を取り除いたRO水のみを扱っているメーカーもあれば、天然水の中から硬水・軟水を選ぶことができるケースもあります。便秘解消には硬水が効果的で、スキンケアや赤ちゃんのミルクを作る時には軟水が良いと言われていることから、用途に合わせて選ぶ人も増えてきています。水の種類によって値段は多少変動します。またサーバーをレンタルするか買い取りするかによっても値段が異なる場合があります。
ウォーターサーバーの衛生管理がどのように行われているのかにも注目できます。サーバーの水は水道水と異なり塩素消毒がされていないため、空気に触れると雑菌が繁殖しやすくなります。それでメーカーとしての管理体制がどのように行われているのかを事前に知っておくなら、安心して利用することができるでしょう。基本的には月に一度のセルフメンテナンスと年に一度のメーカーによるメンテナンスが行われます。メーカーによっては、サーバーそのものに雑菌を除去する機能が備わっているものもあります。
- 冷蔵庫の省エネ化はすごい
- 2015.12.26 リノベーション
-
家庭における電力消費量のうち、およそ20%という大きな割合を占めるのが冷蔵庫です。生鮮食品を保存する冷蔵庫は、季節によって使用頻度が変動する冷暖房器具とは異なり、「今日は使うのを我慢してみよう」ということができません。24時間365日電源に接続されていて稼働し続け、電力を消費し続けます。そのため、リフォームなどで買い替えを考える際にはできるだけ省エネ性能が高いものを選びたいという人が多く、そのニーズに応える製品も続々と登場しています。
450Lサイズで比較すると、2015年のモデルは1年間におよそ200kWhから250kWhの電力を消費します。2000年辺りのモデルでは約700kWhの消費電力でしたから、省エネ性能は格段に向上していると言えるでしょう。内容量が大きくなればそれだけ消費量も増えるように思われがちですが、実は600Lサイズでも電力消費が200kWh前後のモデルが多く発売されているので、無理に容量の小さいものを選ぶ必要はありません。詰め込み過ぎると逆に冷却効率が低下して消費電力が増加する可能性もあるからです。ですから家族のライフスタイルにあったサイズの冷蔵庫を選びましょう。家族2人であれば350L以上、家族4人なら500L以上のタイプを選べば、日常の必要品に加えて予備スペースも十分に確保できます。以前は、一人当たり容量として70Lを確保し、家族人数を掛けてから予備に100Lを加算といわれていました。しかし最近ではお米や、味噌、醤油などの調味料、保存用飲料水なども冷蔵庫に収納する家庭が多くなっているので、さらに収納庫分として100Lを加算することも考えましょう。
リフォームと同時に買い替えを考えている場合は、冷蔵庫用のスペースを事前に計測しておくことが大切です。高さと幅、それからコンセントの位置に注意しましょう。またスペースにぴったりではなく少しの隙間があることで放熱スペースが確保され、省エネにもつながります。
- 洗面所とお風呂場の段差を解消しよう
- 2015.12.26 バリアフリー, リノベーション
-
洗面所と浴室の間に段差があるのは当たり前、と以前は考えられていました。ある程度の高低差があれば、お風呂のお湯が溢れたとしても洗面所に入り込んで水浸しになってしまうことを避けることができるからです。それでも最近では、この段差を上り下りする時にバランスを崩してしまったり、また洗面所の床が濡れていたために転倒して怪我をしてしまうケースが増えてきました。そのため近年では、特に年配者が住む家においてこの段差解消のリフォームが頻繁に行われています。
多くのケースでおよそ8cmから10cmの段差があるため、その解消には浴室扉の変更と洗面所の床リフォームが行われます。浴室扉が内開きの場合には出入りのスペースがかなり制限されてしまい、つかまって支えにできる場所もないために、段差の影響でバランスを崩してしまいやすいものです。そこで扉を折戸に変えて、そのレールを排水に利用することで、段差がなくても洗面所に水が入り込んでしまう事態を避けることができます。また浴室床に大きめの排水溝を設置することでいっそう水はけを良くし、転倒の危険を減らしたケースもあります。
洗面所の床は、高さを下げると同時に滑りにくい素材を使用することでさらに転倒の危険を減らすことができます。洗面所の床を下げることが不可能な場合には、浴室側の足元へ滑りにくい素材の小型スロープを設置することで、段差を心配することなく洗面所との出入りができます。また浴室全体にすのこを引いたケースもあります。こうすることで段差解消だけでなく、床に直接座ることができるので、足腰に不安のある人にも安心です。